The 21st Elizabeth Cup
こんにちは!今回は初心者ながら見事エリザベスカップでルーキープライズを獲得した岩本啓汰さんにブログを執筆していただきました。ぜひご覧ください!
皆さんこんにちは。KDS27期の岩本啓汰です。KDSに入って一ヶ月弱しか経っていない僕ですが、もう既にディベートの沼にどっぷり浸かってしまった気がしています。笑
これからもどんどんディベート力を磨き上げて、KDSブログに再び登場することができた時に、このブログを見た人が「そういえばこんな奴いたな」ぐらいに思い出してもらえるよう精一杯書こうと思うので、最後までお付き合い頂けたら嬉しいです。笑
Table of Contents
1, 自己紹介
2, Elizabeth Cupまでの練習について
3, Elizabeth Cup当日の話
4, 謝辞
1, 自己紹介
僕は文学部人文社会学科一年KDS27期の岩本啓汰です。KDSの他にはテニスとアカペラのサークルに入っています。(テニスやカラオケはとても好きなので、誘っていただけたらいつでも行きます。ぜひ誘ってください先輩方!笑)出身高校は中央大学附属横浜高校です。高校では六年間ずっとテニス部でした。ディベート経験は全くなく、非帰国生なので、いわゆる英語を普通に喋ることもままならない超初心者というやつです。
そんな超初心者の僕がKDSに入った理由は主に二つあり、一つ目は英語のスキルアップになると思ったから。二つ目は兄の影響が大きいと思います。
僕には五個上の兄がいて、その兄がディベートをしているのを見聞きしていました。なので、ディベートってそんなに面白いんだ、どんなものなのだろうという興味はずっと僕の中に湧いていたのだと思います。
2, Elizabeth Cupまでの練習について
今回の大会では、KDS26期の飯森康太郎さんに組んで頂きました。僕は前述した通り、完全に初心者だったため、「ディベートは何をする競技なのか」、「では実際にどのようにスピーチを考えたら良いのか」を学ぶことから始めました。そしてレベルが上がっていくにつれ、SQ、AP、Impactなどの基礎的な立論の仕方を教えていただきました。
実際に大会の練習が始まるまでは、ひたすらスピ練(一つのMotionに対して、自分の考えられるArgumentを出し、それに付随してMechanismやExampleを付け足していくといった、自分のスピーチを磨く練習)を行いました。この練習では、七分どころか一分も喋れたか怪しいぐらいで、もう自分は全く喋れないのだと少し心が折れたことを覚えています。
そこで僕はまず兄に助けを求めました。兄から教えてもらったことは主に三つです。
-
- 七分で話せることは限られてるから、まずこの論題では何を話すべきなのかを精査しろ。(Spirit of Motionが何なのかを考えろ。)
- どの論題であっても対立軸(例えばワークライフバランスVS給料など)を考えろ。
- 論題を自分のサイドにとって有利なコンテクストに持っていけ。
というものでした。
これらの助言はその後の練習、大会でも僕の根本の考え方となる大切なものとなりました。兄よ、ありがとう。
次に、飯森さんとの大会に向けた練習が始まってからの話をしようと思います。
飯森さんとの練習は、ラウンド練(試合形式)が多かったです。
僕が1stだったため、1stの役割としてまずしっかり自分のサイドの論を立てることに集中しました。
ですが、僕のスピーチは課題が山積みでした。
主に出た課題として、
・スピーチ時間が余ってしまう
・Replyがわからん
・Impactが弱い
の三つがありました。
〈これらをどう解決したか〉
【スピーチ時間に対する解決法】
僕はスピ練でしばらく自分のスピーチを磨いていたこともあり、最初の頃よりは長く、2、3分ほどは話せるようになっていましたが、未だに7分もの長さで話すことに苦戦していました。そこで飯森さんから、「話していることがさっき話したことと同じで、内容のないものだとしても、七分目一杯話してくれた方が2ndにとって楽になるよ」と教えていただき、それからはできるだけ長く、七分喋るように心がけました。そのお陰で、本番の時にはもはや話す時間が足りないレベルまでに話せるようになっていました。(時間足りなくて焦ることもありました。笑)
【Replyわからん問題に対する解決法】
Replyには、自分たちが話したことをまとめる、自分と相手の論の比較(コンパリ)などをするといった役割があります。Replyは1st、つまり僕の役割でした。ですが、スピ練では、自分のスピーチを磨く練習しかしていなかったために、ラウンド練を始めた時は全く勝手が分かりませんでした。そこで僕は22期である齋藤陸さんのリプライレクチャーの動画を参考にして、自分なりのリプライの型を作っていきました。本番にはなんとか普通のReplyにはできたのでは、と勝手に信じています。笑
【Impactの弱さに対する解決法】
飯森さんとのラウンド練では、ほぼ毎回Impactの弱さで負けていました。
そのImpactの弱さには、僕のディベートの考え方が影響していたのだと思います。
僕の考え方は、簡単に書くと
SQ:こんな問題がある
↓
AP:その問題が解決される というようなものでした。
ですがこれだけだとImpactが薄く、Judgeはしっかりと論をとってくれませんでした。そこで、「その問題が解決されるから“どういいのか”」や「その問題が解決されなかったら“どうヤバいのか”」、「そのヤバさがどれぐらいの程度、規模感なのか」、そして「どれぐらいの可能性で起こり得るのか」というものを詰めていく作業により、Impactを埋めていけるということを飯森さんに教えていただきました。この助言のお陰で、本番の際にしっかりImpactを詰めたスピーチができたのではないかと考えています。
3, Elizabeth Cup当日の話
Elizabeth Cupはオンライン大会だったため、飯森さんと三田キャンパスの空き教室から参加しました。そこには、Elizabeth Cupに出る同期も3人ほどいて、ラウンドが始まる前や、ラウンドの間の休憩時間に集まって談笑したことで緊張がほぐれてリラックスできました。(同期と話すのってやっぱ安心しますね。笑)
では、各ラウンドの感想を書いていきます。
R1:THW make political voting mandatory.(Opp,勝利)
おそらく自分にとって最高のスピーチができました。
このラウンドでの自分達のスタンスは、主にirrational voteが増えてしまうのはまずいというものでした。比較的分かりやすいmotionだったため、ImpactやMechanismを詰めて話すことができたと思います。(このラウンドが一番高いScoreでした。)
このラウンドでは、飯森さんが考えてくださった、「radical manifestoの場合、例えばNHKぶっ壊すがあるよね」という例を、僕はbreak NHK(?)的なことを英語で言ったのに対し、飯森さんは日本語で と言っていたことが印象に残っています。笑
R2:THW nationalize the pharmaceutical industry.(Gov,敗北)
このラウンドは、個人的に思考しづらいmotionで、苦しいラウンドでした。
そのため、僕のスピーチはR1よりも例の数が少なくなり、Impactも弱くなってしまいました。プレパの際にもっと先輩に頼ってもよかったのかなと今更後悔しています。笑
また、自分のReplyで、飯森さんから反論するよう言われたことがうまく理解できずに反論してしまったことと、飯森さんがprinciple comparisonをしてないのに、していたと言ってしまったこと(←意味分からんミスすぎる)も反省点です。
R3:THBT high-school students should actively engage in romantic relationships.(Gov,勝利)
問題のラブモです。
このラウンドは終始楽しかったです。
もはや飯森さんと笑いながらプレパしてしまったのを覚えています。
プレパでは、他にArgument思いつかないからもう過激にスタンスとっちゃうかと飯森さんと話しました。僕らの取ったスタンスは簡単に言うと、「この世にいる高校生全員の勉強や運動を頑張るIncentiveは、モテるためである(!?)」というものです。
ラウンドの時も思っていましたが、今考えてみても鬼radicalなスタンスだったなと思います。笑
そのため、OAでボートがGovと聞いた際にとても驚き、飯森さんと一緒にハイタッチしました。その光景は今でも思い出せます。僕らの勝因はインパクトや例の量、そして僕らのそもそものスタンスが崩されなかったということが大きいのではないかなと考えています。
R4では僕は休み、飯森さんはPanelでした。強豪同士のバチバチの試合を聞きながら、ディベートという競技は面白いな、楽しいなという感情が生まれたり、こんなに話せるなんてカッコいいとか、勝手に考えてました。また、飯森さんからJudgeはどのようなことを考えて僕たちのスピーチを聞いているのか、どんな基準でボートを決めるのかというようなことを学べたのは普段の練習では味わえない貴重な体験でした。
【大会を終えた感想】
初めての大会ということもあり、緊張しないかな、テンパらないかなとビビっていましたが、いざ始まってみると練習通り、もしくはそれ以上のパフォーマンスで自分のスピーチが出来た実感がありました。練習の時も大会の時も僕と飯森さんはディベート力を上げることを最重要目的としていて、勝敗にはあまり拘っていませんでしたが、やはり勝てると嬉しいものです。笑
結果として、チーム成績としては二勝一敗、個人成績としては僕がEdward Categoryで4th Best Speaker、Andrew Categoryで9th Best Speakerを頂きました。賞を貰えるなんて考えてもみなかったことで、今こうしてKDSのブログを執筆させていただけていることが、まだ信じられないです。
この大会では自分の問題点も何個も浮き彫りになりました。そのため、この結果に慢心せず、これまで以上にディベート力を上げる事に精一杯努力していこうと思います。
4, 謝辞
まず、Elizabeth Cupを運営してくださった方々本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
また、大会までの期間、僕の練習に付き合ってくださったKDSの同期・先輩方や当日Judgeとして参加してくださった方々、実際に対戦してくださったディベーターの方々も本当にありがとうございました。
そして何よりも、一緒に組んでくださった飯森さん、本当に本当に本当にありがとうございました!!!
飯森さんには、KDSの練習がない日にも練習に付き合っていただいたり、何度も的確なアドバイスをいただけました。
超初心者な僕をディベーターにまで磨き上げて貰いました。
飯森さんは、来年以降僕が先輩としてサポートする側に回った時にこんなに上手くやれるだろうかと不安になってしまうほど頼もしく、尊敬する先輩です。
これからもお世話になるつもりなのでどうかお付き合いください。笑
話したいことはまだ沢山あるのですが、次回KDSブログに登場できた時にでも書こうと思います。(また登場できるように日々精進します。笑)
駄文かつ長文でしたが、ここまで読んでくださり、ありがとうございました!!!

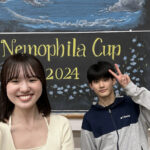 Previous Post
Previous Post Next Post
Next Post